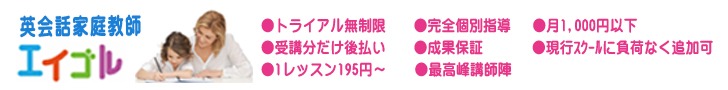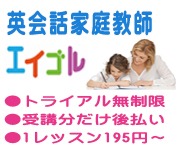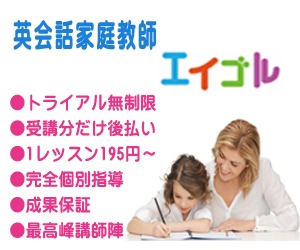介護の英語の読み方とは?
介護士を英語でいうとcaregiver 。ざっくりカタカナにするとケアギバーです。
「私は介護士です」と外国人に言う場合は、「I’m a caregiver」。
つまり、Care(お世話)をGiver(与える人)が介護士なんですね。
日本大百科全書には次のように解説されています。
介護者とは、長期介護のニーズをもつ高齢者や障害者の日常生活上の援助を要介護者の自宅において無償で行う個人であり、要介護者の配偶者や家族、隣人や友人から構成される。イギリス英語ではケアラーcarer、アメリカ英語ではケアギバーcaregiverとよばれる。
日本の知られているのは「ホームヘルパー」です。
漫画の「ヘルプマン!」やドラマ「任侠ヘルパー」でも有名です。
ボクも居宅介護や福祉作業所などに伺うと「ヘルパーさん」と呼ばれますし、介護の仕事で最も知られている呼び名かもしれません。
もともと病気や障害で家事に支障を来たす場合に派遣される人は「家庭奉仕員」と呼ばれていました。
それが平成3年にホームヘルパーの呼び名に変更されました。
ちょっと乱暴に言いますが、ボク個人としては「ヘルパー」という呼び名はあまり好ましく思っていません。
理由としては、なんでもかんでもヘルプする人というイメージが世間に浸透しているような気がするからです。
介護士というのは専門職です。
ヘルパーを否定しているのではありません。
ただ専門職としての地位を向上させ、介護に対するネガティブなイメージを変えたい。
そのためには英語で通用する呼び名を広める必要があると思うのです。
英語での介護コミュニケーション
介護者の規模は国によって違いますが、イギリスは約600万人、オーストラリアは255万人、アメリカは3000~3800万人に上ります(出典:日本大百科全書)。
アジアでも介護者は増え続けています。
特に少子高齢化が急速に進む中国では介護・老人ホームは大きな社会問題になっています。
こうした中、日本の介護は海外で高い評価を得ています。
それだけに今から海外に通用する介護職の呼び名を広めることは意味があると思います。
英語でケアワーカーは介護をする人。
意味は広いです。介護福祉士の資格者もケアワーカーと呼ばれますし、無資格で働いていてもケアワーカーです。
最近では「ケアラー」という言葉も少しずつ広がっています。
ここらへんの定義は非常にあいまいな気がします。
日本ケアラー連盟によると、ケアラーは家族など無償の介護者、ケアワーカーは職業としての介護者、ワーキングケアラーは働くケアラーと位置付けているようです。
余談ですが1990年代に大流行したのが「アムラー」や「シノラー」など「~ラー」でした。
英語の「○○する人」を表す接尾辞「-er」を人物名に付けた和製英語ですが、ケアラーも和製英語のようなイメージがありますね。
英語の用語は必要なのか
結論からいえば、現在の介護現場で英語は必要ないです。
介護業界には楽天や日産のように社内公用語が英語である会社は殆どありません。
どちらかといえば医療用語、たとえばBT(バイタル)やBP(血圧)の方が良く使います。
とはいえ介護施設では年々、外国人の介護士が増えています。
大きな理由は人手不足です。
日本では2008年からはEPAに基づき外国人の受け入れ制度が始まり、インドネシア、フィリピン、ベトナムなどから多く入国しています。
そこで今後、必要とされるのが英語が出来る介護士なのです。
英語を話せる介護士の求人
今後、ますます増える外国人介護士。
彼らをフォローする人材確保は急務です。
とくに日本の介護施設には英語を話すフィリピンの人は多いし、インドネシアやベトナムの介護士も英語を話せる人は少なくありません。
現場で働いて痛感するのはコミュニケーションの難しさです。
日本人同士でも摩擦があるのですから、海外からきた介護士を英語でフォローできる人材は重宝されます。
また、日本で暮らす外国人の高齢者も増加しています。
外国人でも条件を満たせば介護保険は適用されるので、積極的に受け入れる施設がふえれば英語が話せる介護士の活躍の場は広がります。
「日本式」の輸出~英語が話せる介護人材

政府は今、日本の介護をアジアに輸出させようと力を入れています。
世界有数の高齢社会を支える日本の介護は「売れるコンテンツ」でもあるからです。
こうした流れをキャッチして海外進出を宣言し、介護施設の建設を進めている大手企業もでてきています。
海外には日本の介護施設のノウハウを現地で展開し、利用者を獲得しようと考える富裕層も少なくありません。
海外で展開する場合のセオリーは主に富裕層をターゲットにしたビジネスです。
海外の金持ちはハンパじゃありません。
少数精鋭の介護施設では、良質な人材の確保のために給与水準も高い。
この時、英語は強い武器になります。
今後キーワードとなるのは「認知症」だと考えています。
超高齢者で平均寿命が延びると認知症を発症する可能性は高いです。
質の高い認知症のケアができる介護士は富裕層を中心に海外でもニーズは高くなるでしょう。
認知症先進国でもある日本の介護のやり方を海外の施設で提供できる介護士は引き合いも多く、高収入を得られる。
そのためにも最低限度の英語力は必要です。
国際規格で世界の市場をリードできるか
さんざん英語、英語と言ってきましたが、恥ずかしながらボクは英語が得意ではありません。
英語の勉強をしているものの一進一退を繰り返す日々。
英語は好きなのですが、英語がボクを嫌いなようです。
これは個人的な問題ですね。
とはいえ、やはり介護の国際化を見据えると英語力はあって損はありません。
むしろバイリンガルより、トライリンガル(三か国語)を目指したい!(目標は高く)
そして今後のカギを握るのは、国際標準化機構(ISO)です。
政府も介護関連の製品をつくるメーカーやサービス事業者が海外市場に出やすくなるように国際規格作りに力を入れています。
日本の介護の現場では、まだまだ英語力を発揮する機会は少ないですが、世界トップレベルの介護技術は海外への輸出に力を注ぐほど将来性があります。
グローバルな視点で介護業界に携わり、高収入を得たい人は今から「英語力」に磨きをかけていて損はなさそうです。
本日もありがとうございました。
サトシ(@satoshi_Jp0415)でした。