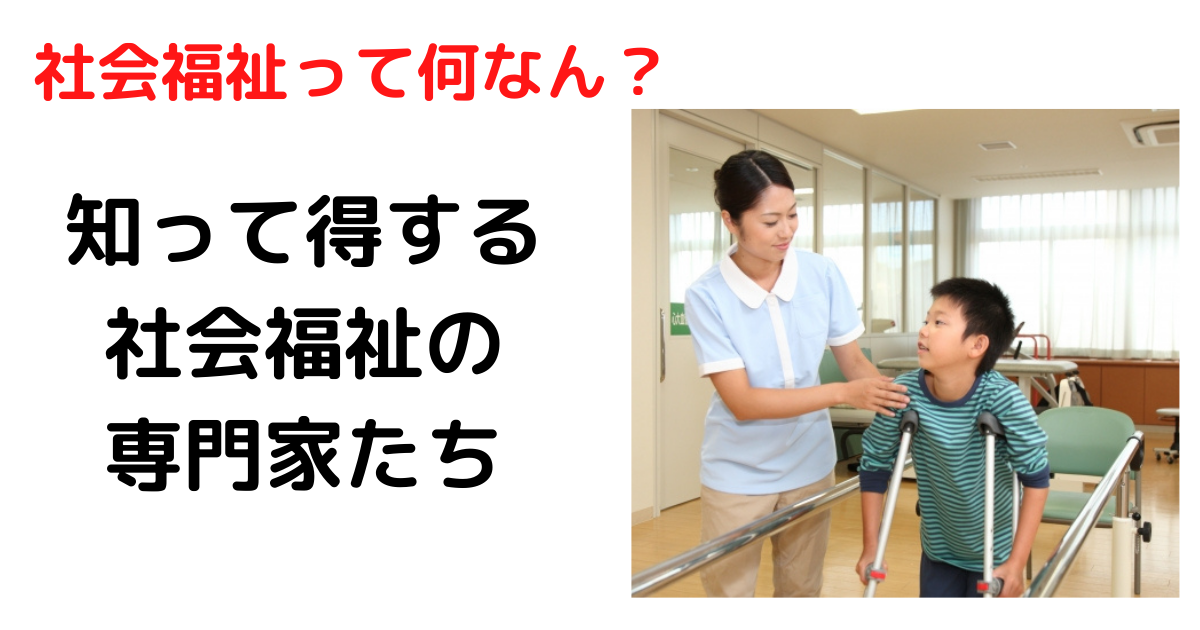
社会福祉の問題点
社会福祉がはたす役割は大きくサービスを知っておくことは大切です。しかし法制度が細かく、サービス内容がわかりずらい大きな問題があります。役所は縦割り行政なので相談してもたらい回しにされるケースは多々あります。この記事では社会福祉の基本と使えるサービスや専門家を解説します。
社会福祉の役割とは?
社会福祉法は人々を守る法律です。社会保障には安全装置の役割があります。仕事が激減して生活ができなくなったり、病気や事故に直面したときの強い味方です。そして困った時は社会福祉のプロフェッショナルがいます。
生活保護法とは
私たちの最低限の生活を担保してくれているのが生活保護法です。日本国憲法第二十五条第一項に「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と記されています。ですから病気や事故、不慮の事態で生活が苦しくても、国が最低限度の生活を保障してくれているのです。
誰だって人生生きていれば、良いこともあれば悪いこともある、予測不可能な出来事は起こります。そうしたときでも国が最低限度の生活は保障してくれます。
8種類の保護
生活保護法に定める保護には8種類あります。すべて現金支給ではありません。医療と介護は現物支給です。医者にかかったら費用がかかりますが、それが無料で受けられるという感じです。
現金のやりとりに慣れていると「なんだ~」と思うかもしれませんが、実はこうしたサービスを無料で受けられるのは恵まれていることなのです。
生活保護法11条によれば、扶助の種類は、①生活扶助、②教育扶助、③住居扶助、④医療扶助、⑤介護扶助、⑥出産扶助、⑦生業扶助、⑧葬祭扶助の8種類です。
利用者負担
福祉サービスの利用者負担は3つあります。応能負担、応益負担、低率負担です。それぞれの意味は次のようになります。
応能負担・・・利用者の経済的能力に応じた負担
応益負担・・・受けた利益に応じた負担
低率負担・・・受けたサービスの一定比率を一律に負担
福祉のプロフェッショナル
社会福祉の専門職は多岐にわたり、様々な名称の専門家が存在します。これが業界をややこしくする一因だと個人的には思っていますが、役割を簡単に紹介します。
保育士
登録を受けて、保育士の名称を用いて、専門的知識や技術をもって児童の保護や保護者に指導を行うことができます。
社会福祉士
専門的知識や技術をもって身体もしくは精神の障害がある方を支援します。また環境上の理由で日常生活を営むのに支障がある方の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、関係者との連絡、調整などの援助を行います。
介護福祉士
身体もしくは精神の障害がある利用者さんを支援します。日常生活を営むのに支障がある方など、心身の状況に応じた介護を行い、その方や介護者に指導を行うことができます。
婦人相談員
都道府県知事や市長が委託します。要保護女子につき、その発見につとめ、相談に応じて必要な指導を行い、これらに付随する業務を行います。
精神保健福祉士
精神保健福祉の領域で専門的な知識や技術を持ち、精神に障がいがある人たちの社会復帰を手助けしたり、必要な訓練を行います。
児童福祉司
子どもや保護者の相談に乗り、問題の解決を手助けする人です。公的機関である児童相談所に所属し訪れる人々の悩みを聞いて解決の糸口を探ります。
身体障害者福祉司
身体に障がいがあるため社会生活や家庭生活に困っている人の相談に応じます。必要な情報を提供したり、生活の実状や環境などを調査した上で、社会的に自立できるよう指導・支援します。
知的障害者福祉司
福祉事務所や知的障害者更生相談所に配置が義務付けられている職員です。知的障害を持つ方に情報提供や相談対応、事務所内の職員への指導などを担当します。
知的障害者相談員
知的障害者、またはその保護者の相談に応じます。そして指導、助言、および知的障害者の更生のための必要な援助を行う民間の協力者です。
身体障害者相談員
身体障害者、またはその保護者の相談に応じます。そして指導、助言、および身体障害者の更生のための必要な援助を行う民間の協力者です。生活上のさまざまな相談に応じ、必要な制度を活用できるよう援助します。福祉事務所などとのパイプ役になったり、社会参加に関する地域活動や行事を公的機関、関係団体と協力したりします。地域住民の理解を深めるため、各種の啓発活動にも取り組みます。
社会福祉主事
都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村に置かれる職です。福祉事務所を置かない町村においても社会福祉主事を置くことができます。生活に困っている人、障害を持った人、高齢者など、何らかの理由で社会生活を送ることが困難な人のサポートします。
まとめ
社会福祉業界は、その中で働く人も分からないほど細かくサービスが分かれています。正直な話、役所の担当者と話をしても「縦割り行政なのですみません」という言葉が返ってくるほど、横のつながりには期待できません
介護保険法、障害者総合支援法、児童福祉法などなど法律を知らなければサービスを利用できないケースも多々あります。それらをどのように組み合わせれば最適なのかを計画できる専門家は少ないです。とはいえ社会福祉サービスはきちんと使えば生活を守ってくれる制度です。困ったときは迷わず活用しましょう。
本日もありがとうございました。
