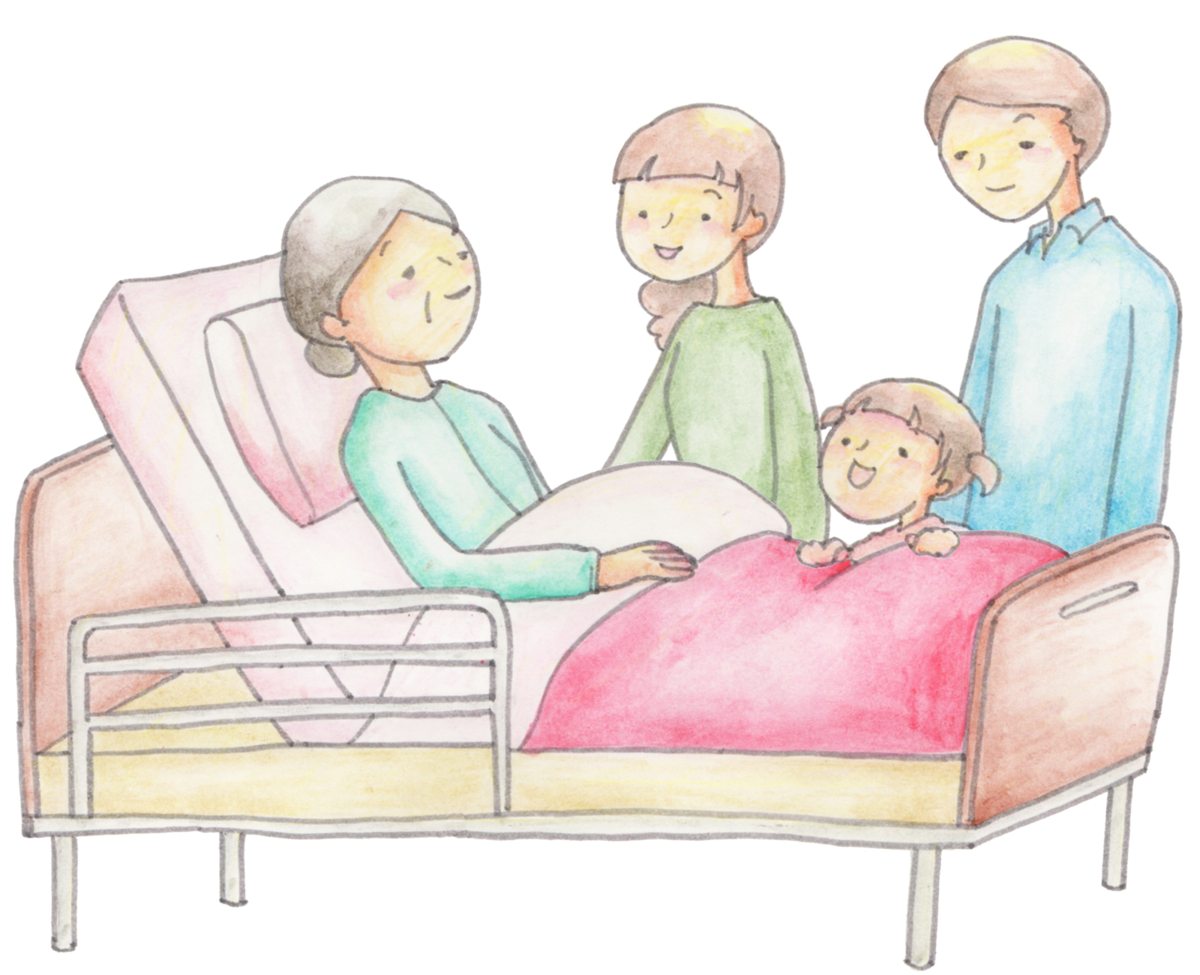
障害と高齢者はサービスが違う
介護と障害では、呼び名は似ていてもサービスは異なります。高齢者の「訪問介護」と障害者の「居宅介護」では対象者も内容も違います。これは介護保険法と障害者総合支援法という法制度の違いによるもので現場でも混乱します。今回は訪問介護の種類や特徴について紹介します。
高齢者の「訪問介護」
訪問介護では、次の条件を満たすことが必要です。
要介護認定を受けた方で、かつ「65歳以上の第1号被保険者・第2号被保険者特定疾病等で認定を受けた40歳~64歳の方」
ほとんどの利用者は65歳以上のシニア世代です。訪問介護サービスを提供する根拠となる法律は「介護保険法」。40歳から介護保険料の支払いが始まるので、ご存知の方も多いと思います。
居宅サービスの内容と特徴
居宅サービスとは、介護保険法における「利用者の家庭で生活支援を行うサービス」です。高齢になり自宅で介護が必要になったときは、このサービスが利用できます。主に6種類のサービスがあります。
①家庭を訪問するサービス
利用者の家庭を訪問するサービスには訪問介護、入浴介護、訪問リハビリテーションがあります。介護が必要になった時に大変なのは入浴です。訪問入浴には専門のスタッフが来ますので、ご家族の方が行うよりも安心安全に入浴することができます。
②医師の指導の管理・助言サービス
医師の指導や看護師による管理や助言を受けられるサービスには訪問看護、居宅療養管理指導があります。訪問看護では、医師の指示に基づいた医療処置や医療機器の管理、床ずれ予防や処置などが行われます。
③施設に通って利用するサービス
施設サービスには通所介護、通所リハビリテーション(デイケア)があります。通所介護は自宅からデイサービスに行って食事や入浴、リハビリテーション、レクリエーションなどのサービスが受けられます。送迎付きのデイサービスが多いので、足腰が弱くなった方も大丈夫です。通所リハビリテーションは、介護老人保健施設や老人病院などに通ってリハビリを受けるサービスです。
④短期入所サービス
家庭で介護を受けながらも、一時的に宿泊を伴うサービスを利用したい方がいます。例えば家族旅行に出かけたいけど、お爺ちゃんお婆ちゃんが心配で…という方は利用すると便利です。短期入所のサービスには、短期入所生活介護、ショートスティがあります。
⑤特定施設のサービス
このサービスは特定施設入居者生活介護、いわゆる有料老人ホームです。有料老人ホームは施設サービスと思われがちですが在宅でのサービスとなります。つまり位置づけとしては家庭でのサービスとなるので、居宅サービスに含まれるのです。
⑥生活する環境を整えるサービス
日常生活に必要なモノを利用できるサービスです。福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修などがあります。
地域密着型サービス
地域密着型サービスとは主に以下となります。
・夜間対応型訪問介護
・地域密着型通所介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
これらは、地域の特性を考えたサービスです。狙いとしては、介護が必要になった方が、出来る限り住み慣れた土地で生活ができるようにするもの。市町村が事業者の指定や監督を行います。利用できるのも原則、その市町村に居住している方です。
小規模多機能型居宅介護
最近、注目されているのが小規模多機能型介護です。小規模多機能型居宅介護は、訪問・通い・短期宿泊を事業内容としています。基本的に通いが中心になるイメージで、介護支援専門員が配置され、小規模多機能型居宅介護計画を作成します。
小規模多機能型居介護のサービスを受けていると、他の事業所の訪問介後を受ける事はできません。一括して小規模多機能型居宅介護の施設からサービスを受ける事となります。他にも他事業所での訪問入浴やデイケア・デイサービス・ショートステイを受ける事は出来なくなります。
しかし利用者が可能な限り自立した生活を送ることができるよう、施設への「通い」や「短期間の宿泊」、自宅への「訪問」を組み合わせながら支援が行われるので手厚い支援ともいえます。1事業所の1日あたりの定員は定められており、登録人数は29名以下。また、介護報酬は月単位の定額なので安心です。
施設サービスの特徴と内容
施設サービスは、介護保険施設へ入所して利用するサービスです。介護老人福祉施設である特別養護老人ホーム(特老)、介護老人保健施設(老健)があります。介護療養型医療施設もありますが、2023年末廃止される予定です。廃止となった後継として2018年4月に創設されたのが、介護と医療体制が整った「介護医療院」です。
ケアマネジャーのお仕事
訪問介護の計画を立てるのは、ケアマネと呼ばれるケアマネジャーです。ケアマネジャーは介護保険の根幹をなす存在です。介護が必要な方のサービスに関する手続を代行してくれます。介護福祉士からケアマネになるケースは多いです。ケアマネは利用者、自治体、事業所の調整役なので高いスキルが求められます。
運営推進会議
運営推進会議は、小規模多機能居宅介護、認知書対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護および地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う事業者は、義務的に設置しないといけないことになっています。
まとめ
居宅サービスには様々なサービスがあり、その一つが訪問介護です。介護にはお金がかかる、将来が心配だ…という声は現役世代からも聞こえてきます。確かに高級老人ホームに入るためには高いお金がかかりますし、必ずしもバラ色の生活が送れるわけではありません。むしろ老後は、住み慣れた家で過ごしたいと思われている方は多です。
居宅サービスはシステムがややこしいですが、それぞれの特徴を知り、上手に組み合わせるとオーダーメイドの介護が受けられます。窓口になるのは、市区町村の介護保険の担当者やケアマネジャーですが、正直なところ力量には差があります。ぜひご自身でいろいろな情報を集めることをおすすめします。
本日もありがとうございました。